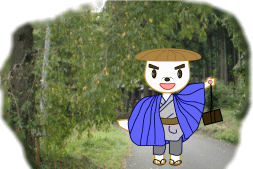|
今回はこの企画を思いついた当初から考えていた中山道のコースです。今年がちょうど開道400年に当たるというのもあるし、かねてから気になっていた摺針峠を越えようと思ったからなのだ。今JR米原駅の西側は何の変哲もない平野が広がっているけど、昔は一面内湖が広がっていたんだ。(昔琵琶湖にはこの米原の他にも近江八幡あたりにも、いくつも内湖があったんだけどほとんど埋め立てられて農地になってしまった。近江八幡は大中という地名がついて、近江八幡市、安土町、能登川町に広がる農業地帯になっています。蛇足でした。)
今の米原駅周辺を考えると国道8号線から21号線に抜ければ楽なんだけど、昔は内湖だったということもあり、峠を越えていったのだ。こんなところにも近代化の影響がうかがえるんだね。そういうことで昔の人達のように歩いて峠を越えることに決めたのでした。
|
|
今回の出発地は近江鉄道鳥居本駅。当日は西武ライオンズが優勝した翌日だったけど、特に優勝記念便乗企画はやってませんでした。(近江鉄道は西武系列の地方鉄道で、日本一運賃が高いことでも知られている・・・。)でも、「優勝記念ありがとうポスター」だけは米原駅に張ってました。右は鳥居本駅正面(上)と、今時珍しい厚紙で出来た切符(下)。ほんとにローカルなのだ。切符は購入するときに駅員さん(嘱託職員ぽいおっちゃん・・)がこれまた懐かしの切符きりではさみを入れてくれました。乗客は日曜の昼間とはいえボクを入れて3人・・・。それにしても初乗り230円はちょっと高いような気がするなぁ。
|

鳥居本駅前にて
|
|
|

表(上)と裏(下)
|
|

現在の鳥居本宿
|
鳥居本駅を出発するとそこはもう中山道63番目の宿場町鳥居本宿。町並みはところどころにうだつのある白壁の建物が残っています。しかし、宿場町としてあんまり宣伝する気がないのか、ところどころに鳥居本宿という看板と昔何があったのかを記す看板が点在しているのみでした。とくに観光客が訪れるという雰囲気ではないようです。ただ、鳥居本宿をぬけて国道8号線にさしかかるあたりに昔のなごりをとどめる松と、中山道をしるす立派なオブジェがありました。
|
|

わずかに残る松並木。
|
国道脇の歩道を歩いていくと、前からウォーキング集団が! どうも彼らも逆コースで摺針峠を超えてきた模様。ボクはまだ歩き始めたばかり、がんばるぞぉ。そのままゆくと脇に右のような石碑が建っていました。いよいよ摺針峠を登るのだ。
|

|
|

|
少し進めばそこは峠の頂上だった。 
|
摺針峠の入り口は工事現場の入り口のような所を進みます。なだらかながらも着実に登っていく感じで、ぐねぐねした道が続きます。(山道だから当たり前だね・・・) 15分ほど登ると急に石垣と民家が現れます。摺針峠の頂上まで来たのだ。もっと急な峠なのかと思ったけれど、以外と楽に歩いてくることが出来たよ。
|
|
一番上にある民家の脇には「明治天皇摺針峠御小休所」の石碑がありました。ちょうどその家の奥さんとお話しする機会があり、家の庭に入らせていただきました。その庭からの大パノラマ!(右) 奥さんがいうには東から来た旅人は初めてここで琵琶湖を見ることになり、西から来た旅人はこんなに登ってきたのかと感慨深くなったそうな。天気がいいと西江州(にしごうしゅう:琵琶湖の西岸)や竹生島も見ることが出来るのだって。ここを通ったどんなに気むずかしいお殿様もご機嫌になる場所なんだそう。奥さん、どうもありがとうございました。
|

奥に見える陸地は昔すべて
帆掛け船が浮かぶ内湖だった。
すっかり変わってしまったんだね。
|
|
この摺針峠は宿場町ではないけれど、休憩所として栄え、(峠の茶屋みたいなモンだね)軒数は少ないものの本格的な街を形成していたらしいよ。
|
|

|
摺針峠に別れを告げ、今度はずっと下っていきます。しばらくすると三叉路にぶち当たりました。中山道は左手の道から手前に伸びています。右手の道は鳥居本の奥の集落に続く道となっています。正面に見える道は名神高速道路です。
三叉路の脇に立つ標識→
|

|
|

さすが日本の大動脈名神。
車の量も多いね。
|
三叉路を左に折れ、ここからはかなりの距離を名神高速道路とともに歩きます。100km前後のスピードで疾走する自動車は結構な音と排気ガスを出します。山の中とはいえちょっと空気が悪いかなぁ。でも何回も名神を通っているけど、彦根インターと米原ジャンクションの間の道路の脇に中山道があるとは思わなかったなぁ。意外な盲点だね。全く景色が変わってしまった地区になるのかな?
|
|
名神に沿って北に進むと急に開けてきます。番場宿はもうそこです。番場宿は62番目の宿場町なんだけど、今は面影もなく田舎の集落です。一応中山道番場宿という看板がちらほら見えるけど、とってつけたようで、昔はそうだったんだなぁと思うくらいです。
|
|
しかし番場宿には「蓮華寺」というお寺があります。番場の忠太郎にもゆかりがあり、北條仲時が最後の時を迎えた場所でもあるのですが、その寺に行くには名神の高架をくぐらなければならないのだ。写真でいうとちょうど真ん中の突き当たりに門があります。本当にすぐ高架の側にあり、お寺からもいやがおうにも名神の高架が目に入ってしまう状態。なんか風情が半減してしまうなぁ・・・。
|

|
|
番場宿を過ぎたあたり。
それっぽいでしょ?

|
しばらく休憩させてもらってから再び出発です。左は集落を抜けた辺りの道です。昔の名残をとどめているような感じだね。北陸道米原料金所の下あたりに右の一里塚の碑がありました。このあたり宿場町の名残はなくても中山道の看板・石碑のたぐいはたくさんあったなぁ。
|

|
|
名神米原インターの脇を抜け、国道21号線を横切り今度は東へ進んでいきます。季節柄周りは彼岸花の群生があちらこちらに見られました。田んぼを取り囲むようにして四角い赤い枠をつくっていました。まだまだつぼみが多かったのでもう少しすれば満開になるね。でもいつも思うんだけど、彼岸花は葉っぱもないのに時期が来ればいつの間にか赤い花をつけているねぇ。不思議な花です。
|
彼岸花の群生。

|
|
この中山道は大体国道の脇に集落の道があって、特に歩いていて危険ではないけれど、一部国道と重なってしまうところがあります。河南という集落から醒井という集落に抜ける所がそこに当たるんだけど、歩道もないし結構車は通るしで歩いていて怖かったよ。このまま歩くのは危ないので他に道はないかと辺りを見回したら、あったんです。名神の脇に人しか通れないような側道が。急いでその道を進みました。ああ、一安心。
そうこうするうちにJR醒ヶ井駅前にある道の駅「醒井水の宿駅」に到着しました。日曜日ということもあってすごい人出でした。米原町主催の出店とかもあって大変なにぎわいでした。ここでは永源寺町池田牧場のジェラート、秋の新作「チーズケーキ」味を頂きました。美味しかったよ。
|
|
醒井宿の様子。

|
醒井水の宿駅を後にして今度は醒井の町の中を進みます。ここは61番目の醒井宿。水のきれいな所で、町の中も小川が流れ、水の中では梅花藻が群生しています。保護されているハリヨは直ぐには見つけられませんでした。水槽にいたのは見たけどね。
|

梅花藻の群生。
|
|
こちらは鳥居本や番場と異なり町が観光地として整備されています。水の駅もあるので観光客もそれなりに多かったね。
|
|
醒井を越え、一色という集落を抜けるととたんに人家が少なくなります。ここからはしばらく国道21号線沿いを歩きます。でも、広い歩道があるので特に危険はありません。この辺りはいかにも町の境目といった感じで、コンビニなどが点々としています。途中で再び集落の中を通る道があるはずなんだけど・・・と探していたら、ちょうどモーテルが集中する辺りにひっそりと道が延びていました。しかもモーテルに挟まれて・・・。それにしても田舎のモーテルは何故か人通りが少なそうな所に建ってるんだよねぇ。
|

米原町と山東町の境あたり。
(国道21号線)
|
|

|
再び集落の道を進むと当たり前だけどそこは、モーテルの裏口。すまなさそうに出入り口があるんだ・・・。 でもそばには左のように不釣り合いな立派な松並木があったりして、やはりここは中山道だったんだと思わせてくれます。
|

字がにじんでしまって肝心の本文に何が書かれているのかわからない・・・。何とか「梓関所跡」というタイトルは読める。
|
|
それを証拠に!?しばらく進むと右のようにここに関所があったことを示す立て札がありました。(本当は心配だったんだー。本当にこの道が中山道か。)
|
|
彦根市から米原町を抜けて山東町に入っていました。こうしてずぅーっと歩いてくると、そこの町が観光客に対してどう対応しているのかが如実にわかっておもしろいねぇ。米原町ではここぞという観光施設には案内看板が完備されていました。山東町に入るとどこどこまであと何kmという案内標識が増えました。このあと何kmというのは歩く人にとって大変ありがたい案内です。何々?次に行く予定の北畠具行公の墓まであと1.6km。もう少しだ。
|
|

|
しばらくするとこんもりした山の麓に大きな看板で「北畠具行公の墓」400mと出ていました。見るとどう考えても山の中です。しかし400mだからと予定通り行くことにしました。道は山道、途中からは結構急になりました。どう見ても民間人のものとしか考えられないお墓もあり、本当にこのまま進んでいっていいのかと思いながら登っていくと三叉路になりました。右手北畠具行公の墓、左手徳源院となっていました。そこから登ること50m、お墓の周りはかなり広くなっていて、ベンチもあり公園のようでした。これがホントの墓地公園。(失礼)
|
|
来た道を三叉路まで引き返し、今度は徳源院に向かって歩いていきました。道は苔むしており、ちょっと気を抜くと滑ってしまいます。下り坂なのでちょっと怖かったよ。再び山の麓(今度は北側)に下りてきました。日も大分暮れてきたのでこのままJR柏原駅に向かおうかとも思ったけれども、せっかくだからとあと1kmの徳源院に向かいました。でも残念、徳源院は本堂の建て直しの最中で、あっちゃこっちゃしていました。奥に京極家のお墓もあるはずなんだけど・・・よくわかりませんでした。三重塔はそのままでした。
|

立て直しの真っ最中の
お堂。きれいになったら
また来よう。
|
|

現在の柏原宿の町並み。
|
最後は60番目の宿場町柏原宿へ向かいました。町は昔の名残を残しているけれども、たくさんあった旅籠は1軒も残ってないらしい。そのためか、街道沿いの民家、お店の軒先に昔ここに何が建っていたかを示す看板が吊られていました(右を見てね)。要は想像してくださいってことだね。
|

ここに昔旅籠屋の
白木屋さんがあった。
(ということらしい)
|
|
最後に−今回のコースは距離としては結構ありますが、ほとんどの区間は集落の道または車があまり通らない道で占めています。本文中にもありましたが、一部国道8号、21号を歩かなければならない区間がありますが、ほとんど歩道がついているので安心でしょう。交通量の多い道ばかりなので、清々しい道かどうかは別として。昔の人は1日に4つほど宿場町を越えていったというので、最低これくらいは歩いて旅を続けていたのだと思います。そう思えは現在は旅をするには楽な時代になりました。ありがたや。それではまた、ブンジでした。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2002年9月)
|